こんにちは。
今回は 教材研究 道徳編 です。
4年生で扱う『心と心のあくしゅ』です。
テーマ(内容項目)は親切です。
親切って何のためにするのでしょうか。
「親切にしましょう」とよく言われますが、具体的にどういうことが親切なのでしょうか?
親切はなぜ必要なのか、その本質的な心について、今日は考えていきましょう!
では、さっそく見ていきましょう!
- 内容項目と教材について
- 導入
- 発問・中心的な問い
- 終末・まとめ
1 内容項目と教材について
内容項目
B 主として人との関わりに関すること
「親切、思いやり」
相手のことを思いやり、進んで親切にすること。
目標を改めて見てみると、「進んで親切に」とあります。ここが重要な点です。
相手が求めていない時、進んでする親切は「親切」でしょうか?いえ、それは親切とは言いません。
それは「大きなお世話」と呼ばれるものです。また、言いかえれば「ありがた迷惑」とも言います。
大事なことは、相手の立場に立つことです。相手の気持ちにより添うことです。
相手の立場・気持ちを考えて、共感したり、同情の気持ちが芽生えた時、人は何かをしてあげたくなるものです。
しかし、相手の立場・気持ちを推し量ることを怠れば、その行為・行動はとたんに「迷惑」なものへと変わってしまうのです。
親切は表面上「何かしてあげる」という行動に表れるように子ども達は考えています。
しかし、それが全てではなく、むしろどのような心からその行動をとったのかが重要なのです。
自分本位のものは親切とは呼びません。相手の喜びを自分の喜びとする。ここに親切の本質があります。
とはいえ、それでも何かしらの行動が相手に伝わるものもあるでしょう。
つまりは「親切の形」は様々あるのです。その多角的な見方を子ども達に体験させてあげれればいいですね。
そして、「本当の親切とは何か?」を一人ひとりの中に再定義できれば、授業は成功と言えるでしょう。
教材について 〜あらすじ〜
「ぼく」は、急いで家に帰る途中に、大きな荷物をもってよいしょよいしょと歩いているおばあさんに出会った。母との約束もあり、声をかけようか迷っていた。
すると、おばあさんが石につまずいて転びそうになった。ぼくは思わず、「荷物、持ちます。」と声をかけた。
しかし、「ありがとうね。でも、家まですぐだからいいですよ。」とにっこり笑って言われた。
おばあさんは、片方の足が少し不自由で、歩くのが大変そうだった。
お母さんにそのことを話すと、「いいことしたわね。はやと(ぼく)のしたことは、少しもまちがっていないわよ。あのおばあさん、最近引っ越してきて、病気で体が不自由になっていたのを、歩く練習をしてあそこまで治ってきたそうよ。」と言われた。
数日後、またあのおばあさんに出会った。
おばあさんは不自由な足を一生懸命動かして坂を登っていた。
(ぼくには、おばあさんに何ができるだろう。)
しばらく考えてから、そっとおばあさんの後ろをついて歩いた。
おばあさんは家の前で待っているむすめさんに、「だいぶ歩けるようになったねえ。」と声をかけられていた。おばあさんはにっこりして、それはそれはうれしそうな顔をした。ぼくの心はぱっと明るくなった。
ぼくは、おばあさんと「心と心のあくしゅ」をした気がした。
4年生「心と心のあくしゅ」(日本文教出版)
教材について 〜留意点〜
この教材には2つの「親切」が描かれています。
その、どちらの親切も間違った親切ではないことはしっかり押さえましょう。
- 大きな荷物を持ったおばあさんを手伝おうと声をかけた親切
- おばあさんの思いをくんで、声をかけずに見守った親切
はじめに声をかけ、けれど断られてしまった親切も、しなければよかった、ということではありません。
この思考に陥ってしまうと授業の方向性が崩れてしまいます。
はじめの「親切」も大切だと押さえた上で、2つ目の「親切」のよさを考えさせましょう。
その親切を考える中で、相手のことを理解し、相手に応じた思いやりができることが親切の本質だということを気づかせてあげたいものです。
もう少し具体的に見てみましょう。
今回の授業の中心的な問いは、「表面上の行動をしなくても、親切と呼べるのか。」ということです。
「ぼく」は、おばあさんに初めて会ったとき、荷物を持とうとしましたが断られました。
2回目に会ったときは、声をかけずに後ろをついていくだけでした。
はじめは「声をかける」と目に見える行動を起こしたのに対し、2回目はおばあさんに対して表面上「何もしていない」のです。
・果たしてこれは、親切だと言えるでしょうか?
・「何もしないこと」は親切ではないのでしょうか?
・さらにははじめに断られた「ぼく」の行動は親切だったのでしょうか、それとも迷惑だったのでしょうか?
結論を言うと、「何もしない親切」が確かに存在します。
そして、断られたとしても、その「行動」は親切です。ただ、その背景に「相手に応じた思いやり」を感じ取れるかどうか、です。
親切とは、何かをするだけでなく、何もしない親切もあるのです。
何もしないことが相手の喜びであることを理解し、あえて何もしないことが親切なのです。
親切とは、行動をする・しないではなく、「相手の立場に立って、相手のことを思う」ことがすでに親切なのです。
「ぼく」は親切であり、思いやりをもっている、とも言えます。
2 導入
導入では、本日のテーマである「親切」についてしっかりと想起させましょう。
今回は「親切=何かしてあげる行為」という固定観念が強く子ども達から出るほど、中心的な問いが際立ち、考えや議論が深まります。
T:教師 C:子ども
T:みんなが考える「親切な人」とは?
C:電車で席をゆずる人
C:教科書忘れたら見せてくれる人
C:優しい人、喜ばせてくれる人
(※ある程度たくさん出すことで、より「親切=何かしてあげる行為」が際立っていきます)
T:なるほど。親切な人に何かしてもらったら、とても嬉しいよね。(伏線)
3 発問・中心的な問い
「ぼく」の行動をふりかえってみると、「ぼく」は2回目は何もしなかったよね?
ということは、「ぼく」は親切ではなかったのかな?
子ども達はこの発問で考えが揺さぶられるでしょう。
「親切」とは何か、改めて考える機会になるのです。
そして、おそらくこの2回目の「ぼく」の行為も「親切」だという結論を導き出すはずです。
では、「ぼく」の1回目の断られたけれど声をかけたことは「迷惑」だったのだろうか?
「迷惑だった」「いや、声をかけてもらえたら嬉しいから迷惑ではないはず」など、様々意見が出るでしょう。
そうして、「親切」について多角的な見方を体験させてあげてください。
他にも違う角度での発問も考えられるでしょう。
・この話で親切だった人は誰だろう。
・「ぼく」は親切な人だと言えるだろうか。
・声をかけたとき(はじめ)とかけないとき(2回目)、「ぼく」の心はどうちがうだろう。
・「ぼく」は誘いを断られたけど、足の悪いおばあさんなので無理にでも手伝ったほうがおばあさんのためになったのではないか。
・おばあさんは、手伝ってほしくなかったのだろうか。
・教材名が『心と心のあくしゅ』だけど、いつあく手したかな。
4 終末・まとめ
道徳の授業の終末で価値観を1つに「まとめ」ることは決してふさわしくありません。多様な価値観を認め合うことが大切です。
ここでは便宜上、この授業で学び取って欲しいポイントとして「まとめ」として表記しています。
終末に、もう1度「みんなが考える『親切な人』とは?」とたずねてみましょう。
そうすることで子ども達の学びや変容、自己評価が見えてきます。
- (表面上)何もしない親切もある。
- 相手にとって1番ふさわしいことができることが親切
- 心からの気持ちですること
これらのポイントを押さえられるといいですね!
今日は「4年『心と心のあくしゅ』【親切、思いやり】の授業はどうしたらいい?」
について考えてみました。
一歩前に進みましょう。また次回もお楽しみに。

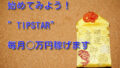

コメント