こんにちは。
教材研究道徳編です。
今日は『4年「いのりの手」の授業はどうしたらいい?』というテーマで教材を解説をしていきます。
内容項目は・・・
【友情・信頼】です。
子ども達に内容項目を問うことはしませんが、教材のタイトルからどんなお話かを想像するのは面白いですね。
今回の『いのりの手』という教材は、個人的にはかなり好きな教材です。
内容項目通りではありますが、「友人との関係」を深く感じられる教材です。
友のために自らを犠牲にすることを厭わない思い。
そしてそれを口にしない、恩にも着せない心意気。
恩返しはお金ではなく自分を支えたその「手」を2人の夢だった絵で返す・・・アツい!
このアツい思いを小学校中学年の全児童が感じ取るのは難しくも思いますが、指導者が持つ思いとしては悪いものではありません笑
ここまで個人の独断と偏見を炸裂させていましたが話は変わって、
今回の「いのりの手」は、定番教材といわれるものの1つです。
1年生の『はしのうえのおおかみ』みたいなものですね。
教科書会社を問わず、長年掲載されている教材、ということです。
定番教材だけあって、様々な実践が繰り返されていますが、それだけ道徳的価値が高いと言えます。
あるいは、深く考えたり、議論する余地がある教材なのです。
定番教材ではありますが、今日の記事をヒントに自分の授業づくりに役立ててください。
では、さっそく見ていきましょう!
- 導入
- 内容項目と教材について
- 発問・中心的な問い
- 終末・まとめ
1 「いのりの手」の導入は、絵のインパクトを大切に!
まずは授業冒頭です。

まずは無言で子ども達に見せましょう。
教室に大型テレビなどがあればインパクトもあってとても良いですね。
子ども達は好き好きにつぶやき始めることでしょう。そこで、こう問いかけます。
「この絵には、どんな思いが込められていると思いますか?」
様々な意見があふれてくると思います。
ここで、想像させることでこれから読む教材分の動機付けとし、本教材を考える上で一貫した視点を持ち、また終末で改めて問い直すことでより『友情・信頼』の理解が深まることでしょう。
・すごくリアル
・何かに必死に祈っている?
・病気になった人が神様にお願いしている手
・亡くなった人に手を合わせている
・平和への願い
やはりそこは「道徳」の授業をしている、という大前提がありますので、児童の反応も相応の答えとなっていましたね。
2 「いのりの手」の内容項目と教材について
内容項目
授業の本題に入って行く前に、改めて内容項目を確認しておきましょう。
B 主として人との関わりに関すること
「友情、信頼」
友達と互いに理解し、信頼し、助け合うこと。
教材について〜あらすじ〜
今から500年ほど前のドイツでの話。 見習い画家のデューラーとハンスがいました。 2人は版画をほる親方のもとで働いていましたが、なかなか絵の勉強ができません。 ハンスが言いました。 「いい考えがある。一人が働いて、もう一人が絵の勉強をするんだ。お金を稼いでもうひとりのために助けよう。相手の勉強が終わったら今度は交代して、もう一人が勉強するんだ。」 ハンスは「デューラー、先に君が勉強しろよ。君はぼくよりちょっぴりうまいからさ。きっと早く進むよ。」 デューラーは「ありがとう。すまない。」と言った。 何年か経って、デューラーの勉強が終わりました。 再開したハンスの手は、鉄工所で長年働いたため、すっかり節くれだち、ごつごつとこわばっていたのです。 「おれの手なんか心配するな。もう絵筆はもてんが、ハンマーを持たせたら天下一品だぞ。」とデューラーをなぐさめました。 「そうだ、君のその手をかかせてくれ。ぼくを絵かきにしてくれた君のその手を。」 その絵は今も「いのる手」と呼ばれています。 この人が、後にいくつものすぐれた絵を描いたアルブレヒト・デューラーなのです。 4年生「いのりの手」(日本文教出版)
教材について〜留意点〜
内容項目は「友情・信頼」と確認しました。
「友情」と「信頼」が2つ並んでいるのは、どちらも考える、と捉えるよりむしろ、どちらかにより重きをおくか?と考えることで教材を捉えやすくなります。
ちなみにこういった内容項目が並列されているものは、同様にそれら全てを扱うよりいずれかに焦点が当てられていると捉えるべきです。例えば、この教材は「正直・誠実」のうち、「正直」の方が焦点だな、と考えるということです。
では、この『いのりの手』は果たして「友情」「信頼」のどちらにより重点が置かれるべき教材でしょうか?
まずは、言葉の意味を確認してみましょう。
友達の間の情愛。友人としてのよしみ。
信じて頼りにすること。頼りになると信じること。また、その気持ち。
みなさんはどちらだと思いますか?
読み進める前に、まずは自分なりに予想してみましょう。
この言葉の意味と『いのりの手』の内容から推測するに…もちろん2人は友達関係であり、「友情」は当てはまる。さらにデューラーはハンスを頼って(信じて)画家になるための勉強に打ち込む。対してハンスもデューラーが必ず画家になると信じてお金を送り続ける。これは「信頼」の証拠なのか…?
この『いのりの手』に置かれている重点は「友情」なのか「信頼」なのか。
それは、視点人物を変えることによって、変化する教材だと考えています。
どういうことなのか?詳しく見ていきましょう。
まずはハンスとデューラーの二人の関係性ですが、もちろん友人同士であり、「友情」関係は成立しているでしょう。一方、「信頼」関係も成立しているといえるでしょうか?
言い換えれば、ハンスはデューラーを、またデューラーはハンスを「信頼」しているのか?ということです。
ここで、少し立ち止まって考えてみる点があります。そもそも「信頼」とはどういうことでしょうか?この言葉をしっかりと理解しておかないと、教師自身がぶれることになりかねません。
よく「信頼」と混同しがちな「信用」という言葉がありますね。
「信用」と「信頼」は何が違うのでしょうか?まずはこれを確認しておきましょう。
信じて用いること
これだけではイマイチわかりにくいですが、「信用取引」や「信用組合」「信用金庫」などを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。
つまり、「信用」とは「担保・保証」があってはじめて成立する関係性です。
対して「信頼」とは、そのような「担保・保証」は一切介在せずに成立する関係性なのです。
「信頼取引」「信頼金庫」なんて商売をしたら、その貸したお金はきっとトンズラされて、間違いなく返してなんてくれないでしょう。担保や返ってくる保証があるからこそ、金利をつけて貸し出す商売が成立するのです。だから、「信用取引」「信用金庫」なんです。
では、デューラーとハンスの間にこの「信頼」が成り立っているでしょうか?今一度考えてみましょう。
<ハンスの視点から>
ハンスは必死になって働いてお金を稼ぎ、デューラーが画家になるための資金とする。もちろん、デューラーからすれば「交代前提」ではあり、それこそが担保であって、「信用」と言えなくもないでしょう。
つまり、この時点では、 デューラーからすればもちろん「友情」前提ではありますが「信用」であり、「信頼」に至っていないとも言えます。
ひるがえってハンスは本当に「交代で勉強する」「君が先に」の言葉通りに思い、行動していたのでしょうか?仮に本当に交代で画家になる勉強をするつもりであるならば、絵筆を持てない手になる前にデューラーに伝えるなり方法はあったと思います。
そして、それをしなかった、つまり担保のない状態であっても相手(ハンスから見たデューラー)が画家になるまで、と信頼しています。
付け加えるならば、デューラーならきっと立派な画家になるという「信頼」ですね。
もしかすれば「絵筆を持てない手になってしまうこと」は途中で気づいたかもしれません。しかし、自分の夢よりも友人の夢を優先した、あるいは自分の夢を友人に託した、とも言えます。
また、当初からハンスはデューラーを信頼しきっていて、「そういう計画」だったのかもしれません。つまり、デューラーを立派な画家にするための方便、ということですね。
どちらにしても、相手に対する「信頼」がなくてはなし得ない行為で、ハンスはデューラーを信頼していたと言えるでしょう。
ハンスが自分は画家にはなれないことに途中で気づいたけれど言わなかったのか、はじめからデューラーに託したのかを子ども達と議論できれば面白いですが、そこは内容項目の本質とは少し離れてしまうかもしれません。
いえ、より深めることができているとは言えなくもないですが、そこに踏み込むにはまだ経験の浅い中学年。少々厳しいように感じます。何より授業時間が足りませんしね。2時間する覚悟であるならばいいですが笑
(子ども達と考えたいポイント)
・ハンスが信じていたことは?
・ハンスは画家になる気はあったのか?(初めから諦めていたのでは?)
・ハンスはどんな思いでがんばっていたのだろう?
・ハンスは幸せだったのか?
<デューラーの視点から>
一方、デューラーの視点から考えてみましょう。
デューラーはハンスの提案を受け入れ、画家になるための勉強に勤しみます。そのための資金はハンスが稼いでくれます。
この時、デューラーはどういう思いでしょうか?
もちろん、ハンスのことを忘れることはないでしょう。
では、何のために画家になることをがんばっているのでしょうか?
・お金を稼いでくれるハンスのために
・ハンスと共に画家になるという約束のために
・自分の画家の夢のために
デューラーにとって、画家になるという夢に向かって勉強するのに必要な資金はハンスによってもたらされるという前提があるのです。友人を思う、友人との約束を果たす、「友情」があるのは間違いないですが、そこには「信頼」足り得るといえるでしょうか?
もし、お金が送られてこなかったらデューラーはどうしたでしょうか?お金がなくても勉強を続けられたでしょうか?
ここに、相手の立場に立つ・相手の気持ちを考えるポイント(友情の深堀り)がありそうですね。
また、ハンスが自分を犠牲にして、デューラーが画家になるために勉強をさせてくれたのは当然うれしかったでしょう。
しかし、ハンスが「もう絵筆は持てん」と言ったことに対して、デューラーは素直に「うれしい」と感じるでしょうか。
「ハンスに勉強して画家になってほしくて、まずは自分ががんばったのに、ハンスの夢が叶わなくなったら、ハンスを犠牲にした自分を責めてしまう。」とは思っていないのでしょうか。(私だったら思いそうです💦)
最後の場面、デューラーはハンスの「信頼」の思いに応えるため、まさに「いのる手」の絵を描いたのです。デューラーが自分を責めたり、否定をしてしまっては、ハンスの行為も思いも否定してしまう。
だからその絵に恩や「友情」の証を描いたのでしょう。これだけのものが描けるようになったのは正にハンスのおかげなのだと証明するかのように。
その思いを子ども達と言葉にしていくことで相手の立場に立つ・相手の気持ちを深く考える「友情」の深堀になるのです。
(子ども達と考えたいポイント)
・デューラーが信じていたことは?
・もしお金が送られてこなくなったら、デューラーは勉強を続けていただろうか?
・ハンスが画家になれないなら、デューラーは自分を責めないだろうか?
・デューラーは幸せだったのか?
3 「いのりの手」の発問・中心的な問い
この教材はどの視点から考えるかで、子ども達と考えるポイントが変わるでしょう。
まずは、ハンスの視点から「信頼」を考えるのか、それともデューラーの視点から「友情」を考えるのかを、授業者が決めましょう。
しかし、気をつけなければいけないのは、決めたからといってそれを子ども達に押し付けないことです。
(若干矛盾を感じるかもしれませんが大事な感覚です)
子ども達がどうやらデューラーに感情移入しそうで、その方が展開しやすいならばそちらに軌道修正もありでしょう。
また、「信頼」と「友情」の明確な線引きが、子ども達全員に理解できるようにする必要もありません。
大切なことは、授業者自身が「何を狙いにするのか?」「何を考えていきたいのか?」「目の前の子ども達とより深められるのはどの選択か?」を考えて授業を展開することです。
- ハンスが信じていたことは?
- ハンスは画家になる気はあったのか?(はじめから諦めていたのでは?)
- ハンスはどんな思いでがんばっていたのだろう?
- ハンスは幸せだったのか?
- デューラーが信じていたことは?
- もしお金が送られてこなくなったら、デューラーは勉強を続けていただろうか?
- ハンスが画家になれないなら、デューラーの努力は無駄だったのだろうか?
- デューラーは幸せだったのか?
- 2人はあきらめようとはしなかっただろうか?
- もしあきらめたくなったことがあったとしたら、どんな心(思い)がささえたのだろうか?
- 2人は信頼関係がある?本当の友達といえる?その理由は?
- (改めて)この絵にはどんな思いが込められていると思いますか?
4 「いのりの手」の終末・まとめ
道徳の授業の終末で価値観を1つに「まとめ」ることは決してふさわしくありません。多様な価値観を認め合うことが大切です。
ここでは便宜上、この授業で学び取って欲しいポイントとして「まとめ」として表記しています。
やはり最後にはもう一度「この絵にはどんな思いが込められていると思いますか?」と問いかけましょう。
その後は議論なく子ども達のノートに自由に記述させてもいいですね。
子ども達の振り返りの例としては、
- つらいときでも、行動の理由は相手を思う気持ち
- 「友情」(「信頼」)は相手の立場に立って気持ちを考えること
- 相手の思いに応えることも友情
- 言葉に表現できない思い(友情・信頼)がある
などでしょうか。
こんな風にポイントを押さえられてもいいですね。
今日は道徳4年「いのりの手」 の授業はどうしたらいい?というテーマで考えてみました。
一歩でも前に進むために、共にがんばりましょう!
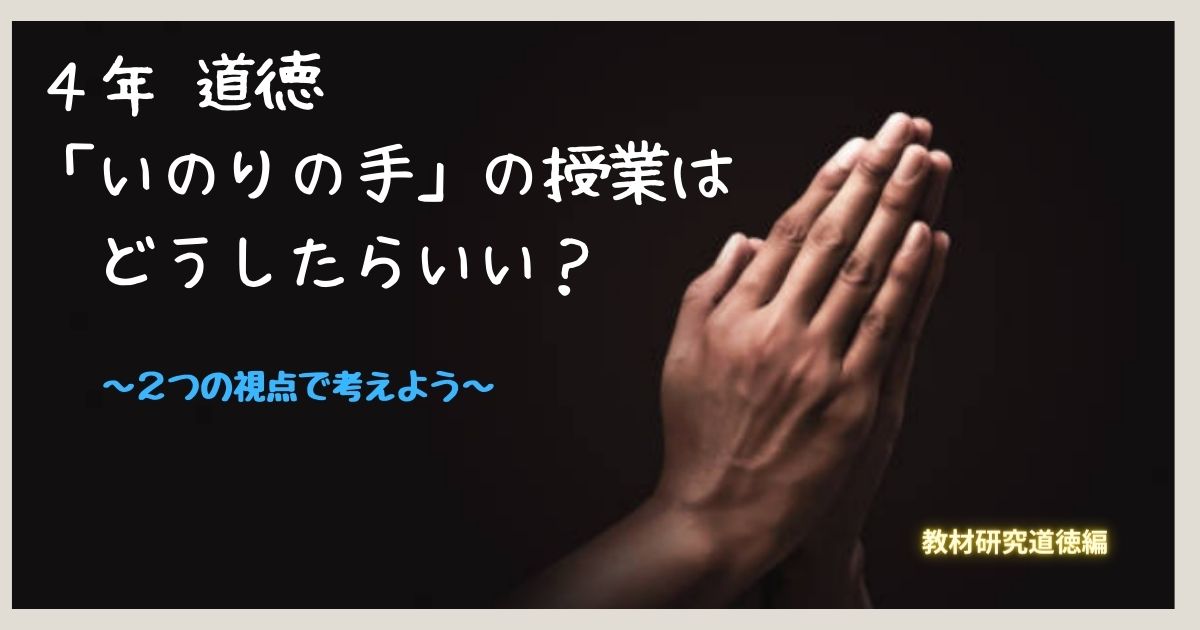


コメント